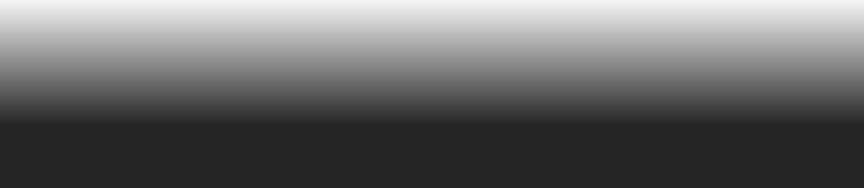
謝辞
一枚の写真に、心を動かされる事がある。
その写真を手にしたのは、1987年 春。
杉山清貴氏の 音楽アルバム『realtime to paradise』のジャケット写真である。
半シルエットの写真にフィルターが巧みに掛けられた一枚だ。
デジタル時代の今では、なんて事のない一枚と思われるかも知れない。
杉山さんの中性的な透き通る 高音ボイスと、詩の世界観に魅せられたのは、
オメガトライブ時代の大半を遡る形で訪れた。
その後、ソロ活動を始めた杉山さんの写真の傍らには、
いつも、Photography Goro Iwaoka のクレジットが記されていた。
『realtime to paradise』のジャケット写真もその一枚だ。
Photographer を志し上京。
晴海で開催された 杉山さんの野外 LIVE『HIGH & HIGH』
7列目から見える景色は、さぞかしLIVE を楽しめたに違いない。
しかし、その夜の記憶は、舞台下のカメラマンに奪われていた。
その時から、純粋にLIVE を楽しめない『宿病』を患ってしまった様だ。
今は、舞台下が自分の定位置であり、招待席では何かが違う。
思い返せば、あの日、Photographer への漠然とした憧れから、
プロの道へと歩み出そうとしていた、心の動きを体感した日であったに違いない。
岩岡さんへアポイントを取る為、意を決し、デザイン会社に連絡を取った。
取り持って頂いたデザイン会社の方には、本当に感謝しています。
岩岡さんも快く会って下さった。
その当時『作品』と呼べる様な写真など、殆ど持ち合せておらず、
さながら岩岡吾郎作品集の様なファイルを、ご自宅へ持参し、熱く語った記憶だけが残る。
岩岡さんは、ファイリングされた写真を観ながら、その時々の撮影話しと、
御自身の出版された写真集や届いたばかりのツアーパンフを前に、
学生時代から今日までの写真との関わりを話して下さった。
色々な質問をしたと思うが『最後の質問』だけは、今もはっきりと覚えている。
『私でもカメラマンになれるでしょうか』
今思えば、無謀な質問。
しかし、そんな私の問い掛けに、 岩岡さんは 躊躇なく、
『なろうと思えば、なれるよ』と優しく答えて下さった。
その言葉は、雲の上から差し込む、一筋の光の様だった。
まずは、レンタルスタジオに入って勉強するといいだろうと、
当時、六本木にあった写真スタジオを岩岡さんに勧められた。
それが、アートセンター入社のきっかけだ。
それから、アートセンターで岩岡さんの入られる音楽誌の撮影には、
すべて名乗りを上げた。しかし、下っ端に権限があるはずもなく。
撮影に入った先輩や、サブに入った同期仲間にスタジオワークを聞き倒した。
撮影に入れた日は、緊張もしたが、どれも心の底からわくわくした。
色セロファンを掛けたものや、光の三原色を巧みに使ったもの、
一灯一灯、丁寧に置かれていくストロボ使いに心が躍った事を、今でも覚えている。
10灯以上のストロボを、出来る限りのスピードでセッティングし、
すべてをシンクロさせる大変さ、燃え易い色セロファンへの気配り、
全ストロボの発光確認をしながら、コードの海を踏まない様に駆け回る。
めまぐるしく押されていくシャッターに、早さを要求されるHasselのフィルムチェンジ。
岩岡さんは『被写体にあまり多くを求めない』そんな撮影スタイルだった気がする。
スタジオに漂う空気感。
ストロボのチャージ音。
閃光と共に響くシャッター音。
その何もかもが、今もなお記憶の中で輝いている 懐かしい思い出だ。
アートセンターを離れてからは、数々のスタジオ撮影、ロケ撮影、LIVE 撮影に、
アシスタントとして、声を掛けて頂いた。
潮風の中、特殊効果の予測に翻弄された THE ALFEE 千葉マリンスタジアム
夏の雨の中、レインウェアを纏い、ずぶ濡れになった、PRINCESS×2 西武球場 2days
終始、走って走って追い続けた 米米CLUB 横浜アリーナの円形可動ステージ
どのLIVE 撮影も、スタジオ撮影も、記憶に残るものばかりだが、
一番多く、ご一緒させて頂いたのは、佐野元春さんの撮影だった。
岩岡さんは、佐野さんのデビュー当時から、ずっと撮り続け、並走されていた。
アシストでご一緒させて頂いた際、バックステージでのお二人の距離感が、
とても心地良く感じられたことを覚えている。
ひとりのアーティストを何十年も撮り続けていれば、馴れ合いが生まれたりするもの。
しかし、岩岡さんはアーティストの大切にしているLIVE前の時間・空間を尊重し、
空気の如く、撮影をされていた。
心地良い緊張感と、心を許されている特別な感じが溶け合っていて、
その光景は、年月を重ねた『信頼』なのだと私は思った。
その後、私にも『撮り続けたい』と思うバンドとの出会いが訪れた。
まだまだ拙く、岩岡さんの足元にも及ばない、手焼きプリントだったと思うが、
一枚、一枚、丁寧に見て下さった事を、今も覚えている。
後にも、先にも、この一回だけだ。
その時、岩岡さんに頂いたアドバイスは、今も胸に残る。
『被写体に惚れ込むことは大切なこと。しかし、好きになり過ぎても駄目。
撮り続けたいなら、冷静に、程よい緊張感と距離感を保ちなさい』というものだった。
岩岡さんと佐野さんの距離感を肌で感じていた私には、その言葉の持つ意味が、
すぐに理解できた。
眼鏡姿の岩岡さんは、肩から 標準・中望遠レンズの二台のカメラに、
首からパノラマカメラを一台下げている。
舞台後方に据え付けたカメラを操作するリモコンと、
予備フィルムの入った、大きな斜め掛けの黒バック。 耳栓。
これが、いつもの装備だ。この出で立ちをいつも左斜め後ろから見ていた。
私は、肩から広角と望遠のカメラ二台を下げ、交換アシスト。
剥き出しの数十本の高感度フィルムを携え、フィルムカウンターをチェックしながら、
今、この距離で、どの長さのレンズが求められているかを予測し、
カメラの受け渡しを、何度も何度も繰り返し、フィルムを交換して行く。
そんなアシスト作業の中で、私のLIVE 撮影の基盤は、構築されていった。
アシストを重ねる中で、ある日、『明日は自分のカメラを持っておいで』と言われた。
THE ALFEEさんのLIVEで撮影させてもらえたのだ。
ステージの高さも、照明の光も乏しい三軒茶屋のライヴハウスで、
撮影の練習をしていたあの頃、
ホールで覗くファインダーの向こうは、音も光も満ち溢れた、美しく輝く別世界だった。
それから、武道館・アリーナクラスの撮影では、最上階からの全景、特効カットや、
バックバンドの撮影を任された。
『無駄フィルムは切れない』 そんな心持ちだった。
一度きりの特効カットに於いては『絶対失敗出来ない』と緊張した。
私に、アシスタントからカメラマンへのステップを作って下さっていたことを、
改めて今、この回想の中で強く感じている。
アシストする事が精一杯で、気付きもしなかった、あの頃。
あの撮影も、あの撮影も、あの撮影も。 どの撮影も、すべてが繋がっていた。
耳に飛び込む爆音に、舞台上のパフォーマンスはコマ切れ。
特効の設置場所やタイミングを気に掛け、何度も見返すセットリストは、ボロボロ。
岩岡さんが、ムービーさんと接触しない様、障害物に当たらぬ様、
一緒に下がりながら、中腰で、何度も何度も振り返る。
そんな一連の流れと、肌で感じる会場の空気感だけが、私のLIVEアシストの記憶だ。
ピッタリ並走し、同じ場所に居ても、カメラマンとアシスタントは、
全く違うそれぞれの景色を見ている。
岩岡さんの居ない今、『背中越しに広がるあの景色』を見る事は、もう二度とない。
2002年 10月 11日 佐野元春 Zeep Tokyo公演のLIVE 撮影が、
岩岡さんと一緒に入った最後の撮影となった。
いつも、『SOMEDAY』のイントロが流れると、
ファインダーを覗く岩岡さんの横顔から、笑みがこぼれていたことを思い出す。
だからもう一度 あきらめないで
まごころがつかめる その時まで
信じる心いつまでも
SOMEDAY
私の人生の中で大きな意味をもつ『写真』を語る時、振り返る時、その先に進む時、
岩岡さんの存在無くしては、語れません。
この写真世界の中、私を導き、支えて頂いた事に、心から感謝しています。
そして、そのことを、『活せる生き方』と、
導かれた道を『輝く道』として、
あの頃と変わらず、この先も『道標』にして行くことを、胸に誓って。
恩師 岩岡吾郎氏への謝辞とさせて頂きます。
三田村 薫


